「五節句」という言葉、聞いたことはあるけれど、正しい読み方やそれぞれの意味を正確に説明できますか?
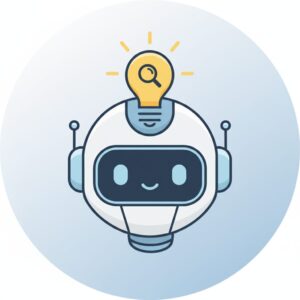
「七草の節句は知っているけど、他の節句はよくわからない…」
「子供に日本の伝統行事を教えたいけど、どう説明すればいいんだろう?」
この記事では、「そもそも五節句ってなんて読むの?」という基本的な疑問から、人日(じんじつ)、上巳(じょうし)、端午(たんご)、七夕(しちせき)、重陽(ちょうよう)という5つの節句について、それぞれの読み方、日付、意味、そして代表的な行事食まで、初心者の方にも分かりやすく一覧で解説します。
この記事を読めば、日本の美しい伝統行事である五節句の知識が深まり、季節の節目をより豊かに感じられるようになりますよ。
五節句とは?まずは読み方と基本を知ろう
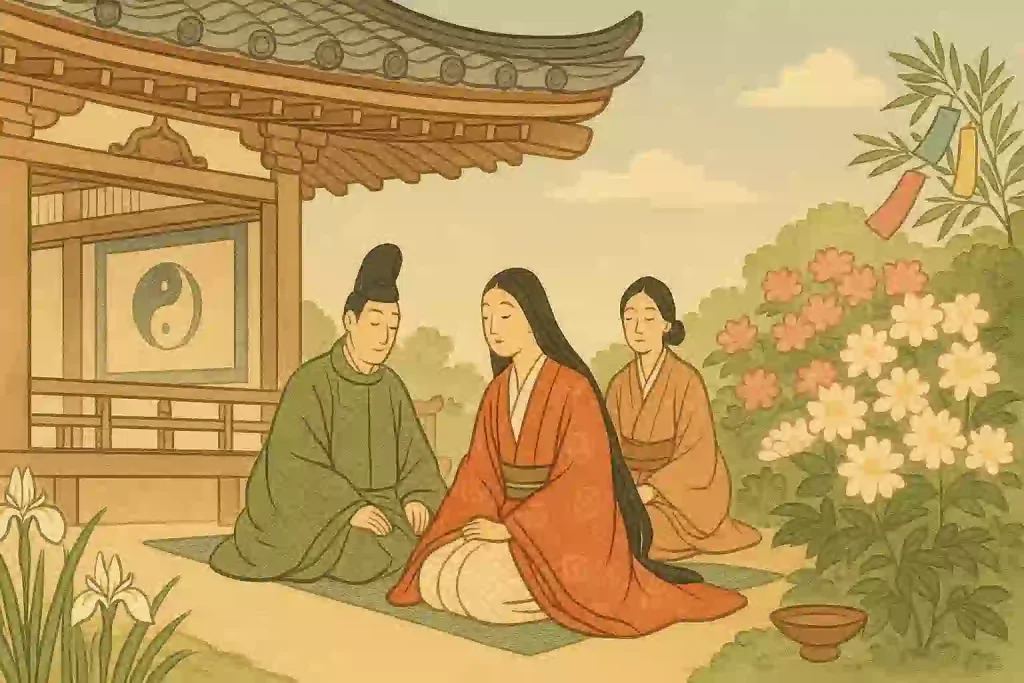
五節句の正しい読み方は「ごせっく」です。
これは、古代中国で生まれた自然哲学の思想「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」が由来とされています。この思想では、奇数は縁起の良い「陽」、偶数は縁起の悪い「陰」と考えられていました。
しかし、奇数でもっとも大きな数字である「9」のように、陽の気が強すぎるとかえって不吉なことが起こるとも考えられていたため、季節の節目となる奇数が重なる日に、お供え物をして邪気を払い、無病息災を願う行事が行われるようになりました。
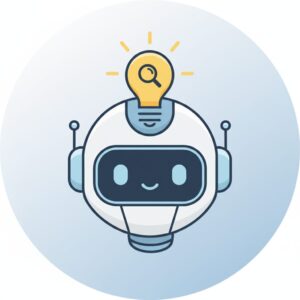
なるほど!奇数が重なる日に邪気を払うという、昔からの習わしが元になっているんですね。
この風習が日本に伝わり、宮中行事として定着。その後、江戸時代に幕府が公式な祝日(式日)として定めたことで、庶民の間にも広く浸透していったのです。
【一覧表】ひと目でわかる!五節句の読み方・日付・意味
五節句の要点を一覧表にまとめました。まずはこの表で全体像を掴みましょう。
| 節句の名称 | 読み方 | 日付(新暦) | 別名・通称 | 意味・すること | 代表的な食べ物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人日の節句 | じんじつのせっく | 1月7日 | 七草の節句 | 7種の若菜を入れた粥で無病息災を願う | 七草粥 |
| 上巳の節句 | じょうしのせっく | 3月3日 | 桃の節句、ひな祭り | 女の子の健やかな成長と幸せを願う | 菱餅、ひなあられ、ちらし寿司 |
| 端午の節句 | たんごのせっく | 5月5日 | 菖蒲の節句、こどもの日 | 男の子の健やかな成長と立身出世を願う | 柏餅、ちまき |
| 七夕の節句 | しちせきのせっく | 7月7日 | 星祭り、笹の節句 | 織姫と彦星の伝説にちなみ、願い事をする | そうめん |
| 重陽の節句 | ちょうようのせっく | 9月9日 | 菊の節句 | 菊を用いて邪気を払い、長寿を願う | 菊酒、栗ご飯 |
それぞれの節句を深掘り!

一覧表で概要がわかったところで、それぞれの節句についてもう少し詳しく見ていきましょう。
1月7日:人日の節句(じんじつのせっく)
お正月の最後の行事として知られる「人日の節句」。「七草の節句」という呼び方のほうが馴染み深いかもしれませんね。
お正月のご馳走で疲れた胃を休め、冬に不足しがちな青菜の栄養を摂るために、春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)を入れた「七草粥」を食べ、1年間の無病息災を祈ります。
3月3日:上巳の節句(じょうしのせっく)
「桃の節句」や「ひな祭り」として親しまれている節句です。「じょうみ」と読むこともあります。
もともとは、紙で作った人形(ひとがた)に自分の穢れを移して川に流すことで、邪気を払う行事でした。これが時代とともに変化し、女の子の健やかな成長と幸せを願って、ひな人形を飾る現在の形になりました。
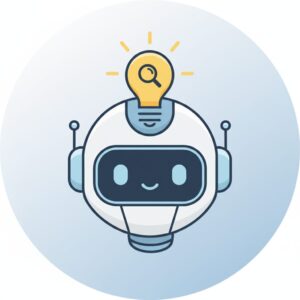
ひな祭りは女の子の特別なお祝いですものね!
5月5日:端午の節句(たんごのせっく)
現在では「こどもの日」として国民の祝日にもなっている「端午の節句」。強い香りで邪気を払うとされる菖蒲(しょうぶ)を飾ったり、お風呂に入れたりすることから「菖蒲の節句」とも呼ばれます。
この「菖蒲」が、武道を重んじる「尚武(しょうぶ)」と同じ音であることから、男の子のたくましい成長と立身出世を願う行事として定着しました。鯉のぼりや兜を飾るのも、こうした願いが込められています。
7月7日:七夕の節句(しちせきのせっく)
「たなばた」の愛称で最も有名な節句ではないでしょうか。
天の川を隔てて会えなくなった織姫と彦星が、年に一度だけ会うことを許されたという伝説は、多くの人が知るところです。短冊に願い事を書いて笹の葉に飾るのは、機織りが上手だった織姫にあやかり、芸事の上達を願ったことが始まりとされています。
9月9日:重陽の節句(ちょうようのせっく)
五節句の締めくくりとなるのが「重陽の節句」です。陽数(奇数)の最大値である「9」が重なることから、非常に縁起が良い日とされています。
古くから邪気を払い、長寿の効能があると信じられていた菊を鑑賞したり、菊の花びらを浮かべた「菊酒」を飲んだりして、不老長寿を願う風習があったことから「菊の節句」とも呼ばれます。
【完全版】五節句の読み方一覧!【まとめ】
この記事では、日本の豊かな四季と、家族の健康や幸せを願う古くからの美しい風習である五節句について解説してきました。
この記事をきっかけに、それぞれの節句に込められた意味を知り、季節の移ろいを感じてみてはいかがでしょうか。まずは身近な行事から、ご家庭で取り入れてみるのも素敵ですね。
