「愛だけでは生活できない。」
これは、長年夫婦として共に過ごしてきたものの、経済的な不安から熟年離婚を考える女性の多くが感じることです。
例えば、A子さん(58歳) の場合——
A子さんは34歳で結婚し、二人の子どもを育てながら長年パートで家計を支えてきました。夫は優しく穏やかな性格でしたが、50代になっても手取り16万円、ボーナスもわずか。子どもが独立した後、「このままでは自分の老後が破綻する」と離婚を考えるようになりました。しかし、離婚後の生活に不安があり、なかなか決断できずにいます。
A子さんのように、「低収入の夫との生活を続けるべきか、それとも離婚すべきか?」と悩む女性は少なくありません。
本記事では、熟年離婚を考える前に知っておくべき現実的な選択肢を、年金分割や夫婦関係修復の方法、住居や仕事の選択肢などを詳しく解説します。
熟年離婚が増えている理由とは?

近年、子供の独立後に離婚を考える「熟年離婚」が増加しています。厚生労働省の統計によると、50歳以上の夫婦の離婚率は2000年と比較して約1.5倍に増加。特に経済的な不安が大きな要因となっています。
熟年離婚を考える主な理由
- 夫の収入が低く、老後資金が不安
- 夫の性格や価値観に我慢できなくなった
- 子供が独立し、夫婦の関係が変化した
低収入の夫との生活が抱えるリスク
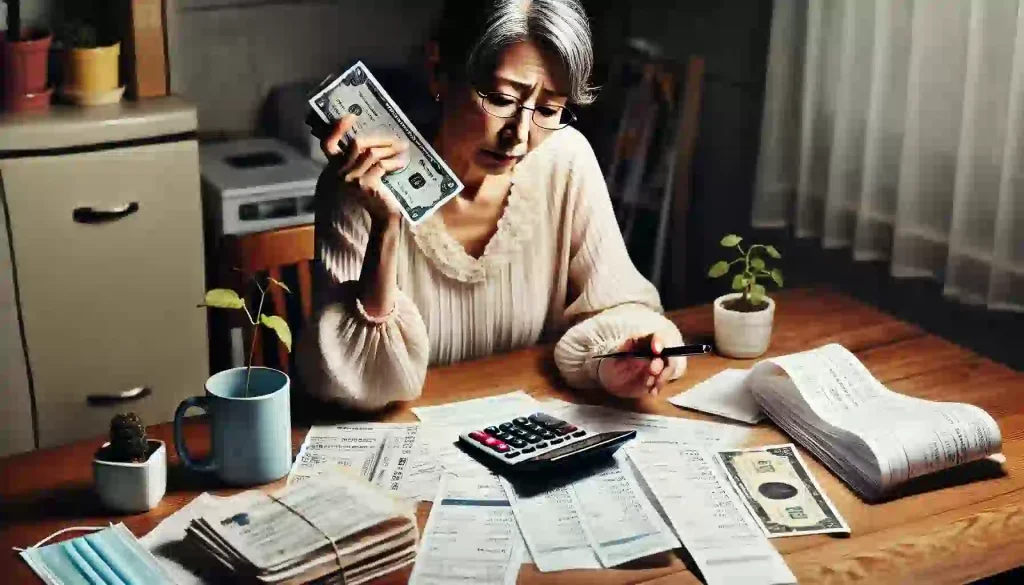
低収入の夫との生活を続ける場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
① 老後資金が不足する
総務省の家計調査によると、夫婦2人の老後の平均生活費は月25〜30万円。しかし、夫の収入が16万円では、貯蓄がなければ赤字が続く可能性が高いです。
② 生活の質が低下する
- 病気になっても医療費が十分に支払えない
- 趣味や旅行などの余裕が持てない
- 夫の退職後、生活費がさらに苦しくなる
③ 精神的なストレスが増える
- 夫が無計画で、生活の改善が見込めない
- 「なんとかなる」という楽観的な夫にイライラする
- 自分の人生を大切にしたいという思いが強くなる
離婚を決断する前にやるべき4つのこと
1. 離婚後の生活費を試算する
離婚後の生活費を把握し、現実的にやっていけるか計算することが重要です。
離婚後の生活費シミュレーション(例)
| 費用項目 | 月額費用 |
|---|---|
| 家賃(賃貸) | 6万円 |
| 食費 | 3万円 |
| 光熱費 | 1万円 |
| 通信費 | 8,000円 |
| 健康保険・年金 | 2万円 |
| 雑費 | 1万円 |
| 合計 | 約14万円 |
手取り収入が10万円以下なら貯蓄を取り崩す生活になるため、厳しい現実が待っています。
2. 財産分与と年金分割を確認する
財産分与
夫婦が結婚中に築いた財産は、原則として2分の1ずつ分けることができます。
- 預貯金
- 不動産(持ち家)
- 退職金
- 生命保険の解約返戻金
年金分割の種類と手続き
年金分割には、**「合意分割」と「3号分割」**の2種類があります。
| 年金分割の種類 | 内容 | 手続きのポイント |
|---|---|---|
| 合意分割 | 夫婦が話し合い、合意の上で分割する | 夫婦間の合意が必要、弁護士を通すケースも |
| 3号分割 | 専業主婦(第3号被保険者)が自動的に分割できる | 2008年以降の厚生年金が対象 |
年金分割を申請する際は、年金事務所で必要書類を提出し、分割割合を決めます。
離婚後の住居はどうする?4つの選択肢

| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 公営住宅 | 低所得者向け。自治体の窓口で申請が必要 |
| 実家へ帰る | 家族と相談し、生活費の分担を決める |
| 家賃の安い地域へ引っ越し | 田舎や郊外は都心より家賃が安い |
| シェアハウスを利用 | 50代以上向けの女性専用シェアハウスもあり |
公営住宅の申し込みは自治体の住宅課で行えます。抽選制の場合が多いため、早めの申し込みが重要です。
50代からでも大丈夫!仕事の探し方

50代でも可能な仕事や資格を取得し、収入を確保しましょう。
おすすめの職種
- 介護職(ヘルパー、介護福祉士)
- 医療事務(病院の受付業務)
- 事務職(データ入力、経理補助)
- 在宅ワーク(ライティング、コールセンター)
活用できる就職支援サービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| ハローワーク | 全国の求人情報、職業相談、職業訓練の提供 |
| シルバー人材センター | 50代以上向けの短期・長期の仕事を紹介 |
| 転職エージェント | 正社員や契約社員の仕事紹介 |
就職支援を受けることで、スムーズに再就職できる可能性が高まります。
まとめ:離婚を考えるなら慎重な準備を!
熟年離婚は慎重な判断が必要です。低収入の夫との生活に不安を感じたら、まず以下のポイントを確認しましょう。
✅ 離婚後の生活費を試算する
✅ 財産分与・年金分割を活用する
✅ 住居の確保と仕事の準備をする
✅ 行政サービスや専門家を活用する
衝動的な決断ではなく、しっかりと準備をした上で後悔しない選択をしましょう。
